公益財団法人川喜多記念映画文化財団
千代田区一番町18番地 川喜多メモリアルビル

映画祭レポート
◇ベルリン国際映画祭 2019/2/07-17
Internationale Filmfestspiele Berlin

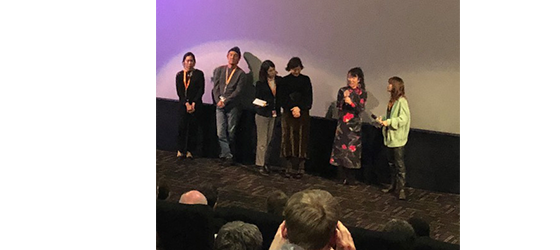





| **受賞結果** | ||||
|---|---|---|---|---|
| 金熊賞 | 『Synonyme』 Nadav Lapid 監督 | |||
| 銀熊賞 | 審査員賞 | 『Grace a Dieu By the Grace of God』 Francois Ozon 監督 | ||
| 最優秀監督賞 | Angela Schanelec監督(『I Was at Home, But』) | |||
| 最優秀女優賞 | Yong Mei(『So Long, My Son』 Wang Xiaoshuai監督) | |||
| 最優秀男優賞 | Wang Jingchun (『So Long, My Son』 Wang Xiaoshuai) | |||
| 最優秀脚本賞 | Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi and Roberto Saviano for La paranza dei bambini (Piranhas) by Claudio Giovannesi | |||
| 芸術貢献賞 | Rasmus Videbak for the cinematography in Ut og stjale hester (Out Stealing Horses/Pferde stehlen) by Hans Petter Moland | |||
| アルフレート・バウアー賞 | 『System Crasher』Nora Fingscheidt監督 | |||
| 最優秀新人作品賞 | 『Oray』Mehmet Akif Buyukatalay 監督 | |||
| 国際批評家 連盟賞 |
コンペ部門 | 『Synonymies』 Nadav Lapid 監督 | ||
| パノラマ部門 | 『Dafne』 Federocp Bondi 監督 | |||
| フォーラム部門 | 『Die Kinder der Toten 』Kelly Cooper, Pavol Liska監督 | |||
|
Berlinale Camera (貢献賞) |
Wieland Speck(元パノラマ部門キュレーター/ ドイツ) Agnes Varda(監督/ フランス) Sandra Schulberg (Founder of the Independent Filmmaker Project/USA) |
|||
|
Honorary Golden Bear (金熊名誉賞) |
Charlotte Rampling (俳優/フランス) | |||
**概観**

|
| メイン会場、ベルリナーレ・パラスト前。 待機するカメラマンたち。 |
少々拍子抜けするほど暖かい日が続いた第69回ベルリン映画祭。今回は2002年以来、18回にわたってベルリン映画祭ディレクターを務めたディーター・コソリック氏の最後の回ということで、記念すべき回であった。勇退に際しての儀式や特別イベントはなかったものの、オープニングセレモニーにおいてはコソリック氏への敬意と感謝のこもったスピーチがなされ、万雷の拍手の中、促されて壇上に上がったコソリック氏が感極まる一幕があり、会場が特別な空気に包まれた。客席にはカンヌ、ヴェネチア、次期ベルリン映画祭ディレクターなど錚々たるメンバーが見受けられ、勇退するコソリック氏を讃えていた。映画人育成のためのタレント・キャンパス(現・ベルリナーレ・タレント)の創設、第三世界の国を対象とした企画プロジェクト支援、料理部門やドラマシリーズ部門の新設、マーケット機能の充実化、そして観客重視の姿勢を前面に出して、より市民に開かれた映画祭へと導いたコソリック氏の功績は大きい。コソリック氏就任後のベルリン映画祭は格段に明るく、近づきやすくなったことは確かである。今ではすっかり定着した赤い熊のシンボルマークもコソリック氏の就任とともに導入されたと記憶している。その一方で、映画祭が肥大化し過ぎてしまったきらいもあり、近年は出品作品の質の低下が繰り返し問題視されていた。もっともこの問題は開催時期などいろいろな要素が絡んでいるので、一概にディレクターの責任とは言い難いのだが…。次回、2020年からは昨年までロカルノ映画祭のディレクターを務めたカルロ・シャトリアン氏がアーティスティック・ディレクターに、ドイツ映画輸出公団 (German Films)のマネージング・ディレクターを務めたマリエッテ・リッセンベーク氏がエグゼクティブ・ディレクターに就任することが決定している。コソリック氏が提唱していた‘ふたりのディレクター’制が実現した形である。三大映画祭のトップの職を女性が担うのは史上初。シャトリアン氏はイタリア人、リッセンベーク氏はオランダ人、シャトリアン氏とともにロカルノから異動し運営に携わるとされるマーク・ペランソン氏はカナダ人と国際色豊かな新体制になる。新体制の正式な発足は6月と目されており、それ以後に発表される人員を含む改革案に注目が集まっている。一つ目の改革案は時期の変更である。すでに2020年の会期は発表され、アメリカのアカデミー賞受賞式の後である2月20日〜3月1日(これまでは受賞式前の開催)とのこと。アカデミー賞前で忙殺されている主にハリウッド系の関係者を呼び込みたいという思惑と推察できるが、その分5月開催のカンヌ映画祭とは間隔が狭まる。

|
| オープニングセレモニー。 司会のアンケ・エンゲルケ氏(中央)の軽妙な進行は 今やオープニングの風物詩となっている。 |
メインのコンペティション部門には17作品が選出されていたが、チャン・イーモウ監督(中国)の『One Second』が上映前日にキャンセルとなってしまった。公式発表としては「技術的な問題のため」とのことであったが、この作品は文化大革命期(1966−76年)が舞台であることから、中国当局から規制がかかった可能性を指摘する見方も多い。実際、ここまでぎりぎりになっての出品取り止めはベルリン映画祭に限らず聞いたことがない。チャン監督はベルリンとの縁も深く、デビュー作『紅いコーリャン』(88年)では金熊賞を受賞しており、それ以外にも複数の作品を出品している。空いてしまった上映枠にはチャン監督の大ヒット作であり、ベルリン映画祭でアルフレッド・バウワー賞を獲得した『HERO』を充填した。また、ジェネレーション部門においても中国・香港合作の『Better Days』(デレク・ツアン監督)が出品取り止めとなった。こちらの理由としては「完成が間に合わない」。中国当局は近年、エンタテインメントや出版等に関しての規制を強化しており、これらの上映中止もその一環ととらえる向きがあるのもやむを得ない。この傾向はどこまで進んでしまうのか・・・。
金熊賞に輝いたのはイスラエル人のナダブ・ラピド監督作『Synonymes』(フランス・イスラエル)であった。監督自身の経験をベースに、イスラエル出身の青年がパリでフランス人に同化しようともがく様子が皮肉とユーモアを込めて描かれた作品である。次点にあたる審査員グランプリは、フランソワ・オゾン監督がフランス・リヨンで実際に起きた神父による性的虐待事件を題材にした『By the Grace of God』。これまでの華のあるオゾン監督作品とは一線を画した骨太な社会派作品で、オゾン監督の「どうしても撮らなくてはならない」という強固な意志が伝わってきた。監督賞とアルフレッド・バウアー賞には、ふたりのドイツ人女性監督の作品がそれぞれ選ばれた。監督賞のアンゲラ・シャーネレク監督の『I was at Home, but』は、ストローブ=ユイレの影響が色濃くみられる作品として、特に批評家筋の評価が高かった。アルフレッド・バウアー賞は、母親に見放され、施設に預けられる問題児の少女を追った『System Crasher』に授与された。

|
| 壮麗なフリードリヒ・シュタット・パラスト前。 開場を待つ人々にプレッツェルがけっこう売れている。 |
昨年来、欧米の映画業界において男女格差を改善する動きが活発化している中、ベルリン映画祭は「男女同比率に関する誓約書」を批准した。カンヌ・ヴェネチア・ロカルノ・トロント等の映画祭もすでにサインをしている。この誓約書には映画祭内での主要ポジションにおける女性の割合を同率にすることに関しても言及されているが、ベルリン映画祭はこの点はすでに達成している。今回の映画祭に選出された400あまりの作品のうち半数が女性監督によるもので、コンペ部門においては17本中7本。明らかな不均衡を正すのに一定の強制力が必要なのは理解できるものの、作品選考に関してはジェンダーの前に作品のクオリティが最重要視されてしかるべきであり、この「同率政策」にすっきりしない部分も感じてしまうが、コソリック氏の言葉として伝えられた「女性監督の作品だからではなく素晴らしい作品だから選ばれた」にひとまず安堵した。コンペティション部門の審査員長はジュリエット・ビノシュ氏が務め、『ありがとう、トニ・エルドマン』(16)で主役を演じたドイツ女優のザンドラ・ヒュラー氏、英国人プロデューサーで女優、トゥルーディー・スタイラー氏、チリ人監督セバスティアン・レリオ氏、ニューヨークのMoMAの映画部門チーフ・キュレーターのラジェンドラ・ロイ氏、ロサンゼルス・タイムスの映画評論家ジャスティン・チャン氏の6名で構成され、半数が女性であった。それ以外の審査員団もドキュメンタリー、短編、新人賞それぞれ3名の審査員のうちいずれも2名が女性。目配りが感じられる比率である。名誉賞受賞の大ヴェテラン、シャーロット・ランプリング氏とアニエス・ヴァルダ氏は堂々たる存在感を示した。そして日本のHIKARI監督を含め、多くの女性監督たちの作品も好評を博していた。ある程度自然な形で女性が存在感を示していたのは喜ばしい。
**日本映画**

|
| 『37 Seconds』Q&A (右から二人目・HIKARI監督) |
今回もコンペ部門に日本作品は入らなかった。パノラマ、フォーラム、ジェネレーション、キュリナリー部門にそれぞれ長編作品が一作品ずつ、ジェネレーション短編部門に一作品が出品された。パノラマ部門の『37 Seconds』は脳性麻痺の若い女性が、自身の障害と向き合いながら成長していく姿をLA在住のHIKARI監督がパワフルに描いた作品。上映時の観客の熱い反応は特筆もので、観客賞も納得であった。映画祭期間中にもさまざまな国から配給やセールス、さらなる映画祭出品についてのアプローチを受けたという。同作はアートハウス系の映画を支援するCICAEアートシネマ賞の受賞も果たした。フォーラム部門には三宅唱監督の『きみの鳥はうたえる』が選出された。大画面に映る函館の気怠さと清々しさがブレンドされた映像美でベルリンの観客たちを魅了した。ジェネレーション(14+)部門には長久允監督の長編第一作である『We are Little Zombies』が、同部門のオープニング作品として出品され、スペシャルメンションを授与された。ベルリン映画祭においてティーンが鑑賞可能なのは同部門のみで、ティーンの審査員により評価を受けたことに長久監督はとりわけ喜びを示していた。また同作は1月にワールドプレミア上映であったサンダンス映画祭において二等賞にあたる審査員特別賞を受賞している。近浦啓監督のやはり長編デビュー作『COMPLICITY/コンプリシティ』は昨年の東京フィルメックスで観客賞を受賞している日中合作作品で、外国人実習生とその周囲の人間模様がスケール感を持って描かれている。ベルリン映画祭は「蕎麦」が同作の鍵になる点に光を当て、キュリナリー部門に選出。ベルリンの観客の人々はいっぷう変わった切り口からの鑑賞を堪能していた。

|

|
| 『きみの鳥はうたえる』Q&A (中央・三宅唱監督) |
『コンプリシティ』Q&A (左から二人目・近浦啓監督) |
今回の日本からの出品作品はいずれも30代―40代前半のフレッシュで、確かな力を感じる新進監督によるもの。さらなる活躍が期待される作り手たちの登場に希望を感じた回であった。


